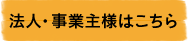1. 「野生の思考」ってなに?
ロード・レヴィ=ストロース(Claude Lévi-Strauss)の著書『野生の思考(La Pensée sauvage, 1962)』は、構造主義人類学を代表する重要な著作の一つです。この本で彼は「未開」とされる社会における思考が、「文明人」の思考と本質的に異なるものではないというラディカルな主張を展開しています。
けして読みやすい本ではありませんが、100分de名著シリーズでも解説本が出てますのでそちらから読むことをお勧めします。(あと野生の思考は手に入りにくい!)
レヴィ=ストロースはこう言いました。
「自然の中で生きてきた人たちの考え方は、私たちと変わらないくらい、むしろとても頭を使っている。」
つまり、「野生の思考」の中で大切にしていることとは、
-
手元にあるもので工夫する力
-
世界を理解しようとする力
-
決まったルールではなく、自分なりのやり方で考える力
などが挙げられます。
これって、まさに「遊び」と似ていませんか?
2. 子どもの遊びは「考える力」そのもの
たとえば子どもが、段ボールを使って秘密基地を作ったり、小枝と石ころでおままごとをしたりしますよね。
大人から見ると「ただ遊んでる」ように見えても、子どもは、
-
ものを分類して、
-
役割を決めて、
-
自分なりの世界を組み立てている
つまり、これは世界を理解しようとしている姿なんです。
🧸 例:
-
保育園で空き箱や落ち葉を使った制作あそび
-
学童保育でのごっこ遊びや自由工作
-
プレーパークでの土や水を使った冒険あそび
これらは「遊び」だけど、「学び」としてもとても深い意味を持っています。
3. 日本の教育現場での実践例
🔸 保育園・幼稚園
-
多くの園では「自由遊び」の時間を大切にしています。
-
子どもたちは自分でやりたいことを選び、試行錯誤しながら関係を作ります。
-
木の枝や自然物を使った遊びは、まさに「ブリコラージュ(あるもので工夫する)」の世界。
🔸 学童保育
-
放課後の自由時間に、子どもたちはルールのない遊びを発明したり、新しい遊び道具を作ったりします。
-
指導員は「教える人」ではなく、「一緒に考える人」として寄り添うことが大切。
🔸 自由保育・オルタナティブ教育
-
レッジョ・エミリアや森のようちえんでは、子どもの「気づき」や「発見」に基づいて活動が組まれます。
-
教材やカリキュラムより、子どもの「今、ここで起きていること」が大切にされます。
こうした実践は、「決まった教え方」ではなく、子どもの思考のプロセスそのものを大事にしています。これはまさに「野生の思考」を生かした教育です。
4. 「教える」から「気づかせる」へ
今の教育は、「正解」を教えることに重きを置きがちです。でも、レヴィ=ストロースの考え方に学べば、次のように考えられます。
-
子どもは本来、自分で世界を観察し、比べ、意味づける力を持っている。
-
教育はそれを「邪魔しない」こと、「引き出す」ことが大切。
-
遊びの中には、すでに「学び」がたくさん詰まっている。
5. まとめ:遊びは「もうひとつの知」
レヴィ=ストロースが語った「野生の思考」は、単なる昔の話でも遠い国の話でもありません。
-
子どもたちが自由に遊ぶとき、
-
工夫してものを使い、
-
他の子とやりとりをしながら、
-
世界のルールを発見していく…
その姿こそが「生きた思考=野生の思考」です。
📌 私たち大人にできることは、「正しい答え」を押しつけることではなく、子どもが世界に驚き、試し、発見する時間と空間を守ることだと思います。
1. 「ブリコラージュ」に関する記述
« Le bricoleur est apte à exécuter un grand nombre de tâches diverses, mais contrairement à l’ingénieur, il n’applique pas des plans préalablement définis. »
「ブリコルール(器用人)はさまざまな作業をこなす能力を持っているが、技術者とは違って、事前に決まった設計図を使うわけではない。」
これは、子どもが遊びの中で見せる「工夫」や「即興性」の思考と強く結びつきます。何かを作るとき、子どもは説明書どおりに作るのではなく、目の前の素材を見て思いつくままに創造していきます。これはレヴィ=ストロースが「ブリコラージュ的思考」と呼ぶものであり、教育の枠組みにとらわれない自由な知性を表します。
2. 「具体の科学(la science du concret)」について
« La pensée sauvage… est une science du concret. »
「野生の思考とは、具体的なものの科学である。」
ここで言う「科学」とは、物理学のような抽象的で理論的なものではなく、日々の観察や体験を通じて、物事を分類し、意味づけていく知のことです。子どもが遊びを通して物の違いを見分けたり、使い分けたりするのも、この「具体の科学」による思考の表れといえるでしょう。
3. 思考の平等性に関する記述
« Il n’y a pas une pensée sauvage d’un côté et une pensée domestiquée de l’autre, mais deux modes de pensée également légitimes. »
「一方に野生の思考があり、他方に飼いならされた思考があるのではない。どちらも正当な二つの思考様式なのだ。」
これは、学校教育における「論理的・分析的思考(≒文明的思考)」が優れていて、子どもや先住民の思考が「未熟で劣ったもの」という偏見を批判する重要な一節です。つまり、子どもの遊びの中にある「分類」「組み合わせ」「象徴化」も、れっきとした知的営みとして尊重すべきだと読み取れます。
4. 神話的思考について
« Le bricolage opère sur un ensemble clos. L’univers de l’ingénieur est celui des matériaux et des outils définis en fonction d’un projet. Celui du bricoleur est celui des moyens du bord. »
「ブリコラージュは閉じられた世界で働く。技術者が使う道具は、計画に基づいて選ばれるが、ブリコラージュは“そこにあるもの”を用いて組み立てられる。」
これは「正解のない世界で、子どもが目の前の素材で意味ある世界を作る」遊びそのものを表しています。学童保育や保育現場でよく見られる、段ボール工作・秘密基地づくり・泥団子遊びなどは、まさにこの思考様式です。