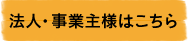学童保育におけるごっこあそびについて
ごっこ遊びの大切さと面白さ
――子どもの想像力と社会性を育む遊び――
ごっこ遊び(「ままごと」「ヒーローごっこ」「お店屋さんごっこ」など)は、幼児期に特によく見られる遊びのひとつです。一見すると単なる「遊び」に思えるかもしれませんが、実はこの遊びの中には、子どもたちの心と体の成長にとって重要な要素がたくさん詰まっています。
発達心理学者ジャン・ピアジェ(Jean Piaget)は、ごっこ遊びを「象徴遊び」と呼び、子どもが現実を自分のやり方で再構成し、理解していく過程と位置づけました。たとえば、バナナを電話に見立てたり、人形を赤ちゃんとしてお世話したりする中で、子どもは「ものを別のものとして扱う力(象徴機能)」を育てています。これは、言葉の理解やコミュニケーション能力の基礎となる重要な力です。
また、発達心理学者レフ・ヴィゴツキー(Lev Vygotsky)は、ごっこ遊びを通じて子どもは「社会的なルールや役割」を学んでいくと指摘しています。たとえば「先生役」や「お医者さん役」を演じることで、子どもは「自分とは異なる立場」に立ち、他者の視点を理解しようとするのです。この経験は「他者理解」「協調性」「自己抑制」など、社会生活に必要な力を育む土台となります。
さらに、ごっこ遊びには「楽しさ」や「創造性」が満ちています。子どもたちは空想の中で自由になり、現実にはできない冒険や物語を展開します。自分たちでルールやストーリーを作り出す過程で、「想像力」や「問題解決能力」も自然と育まれていきます。
保育者として、子どもたちのごっこ遊びをただ見守るだけでなく、その世界に少し入り込み、共感し、問いかけることで、より深い学びや関わりが生まれます。ごっこ遊びは、子どもが「今、ここ」で全力で生きている姿であり、同時に未来への準備でもあるのです。
学童保育におけるごっこ遊びの意義
――子ども同士の関係性と自己表現を育む場として――
小学校に通う子どもたちが放課後を過ごす学童保育の場では、ごっこ遊びが単なる「遊び」を超えて、子ども同士の関係づくりや自己理解、情緒の安定に深く関わっていることが、現場の観察や研究から明らかになっています。
幼児期に比べて社会的認知が発達してくる学童期の子どもは、ごっこ遊びをより複雑なストーリー構成や集団ルールの中で展開するようになります。たとえば「アイドルごっこ」「YouTuberごっこ」「探偵ごっこ」「サバイバルごっこ」など、現代的なテーマが加わり、流行やメディアの影響が色濃く反映されます。これは、子どもたちが自分たちの関心や憧れ、社会へのイメージを遊びを通して表現していることを意味しています。
教育社会学者の秋田喜代美(2012)は、子どもは遊びの中で「役割を引き受け」「関係を交渉し」「世界を再構成する」存在であると述べています。学童期のごっこ遊びでは、子どもたちは単に役割を演じるだけでなく、「誰とどう関わるか」「どんなルールを作るか」を自ら話し合い、交渉しながら遊びを成立させていきます。このプロセスは、協調性や合意形成の力、自分の意見を表現し、相手の意見を受け入れる力といった、まさに“生きる力”を育む場になっています。
また、心理学者エリクソン(Erikson)が提唱した「勤勉性 vs 劣等感」の発達課題においても、学童期は自尊感情や達成感を得ることが重要な時期です。ごっこ遊びの中で自分の役割を果たしたり、仲間に認められたりする経験は、子どもにとって「自分はここにいていい」という安心感と自己肯定感につながります。
学童保育では、学校のような「評価」や「指導」から少し離れ、子どもが自由に自己を表現できる場としてのごっこ遊びの価値を、改めて見直すことが求められます。大人は一方的に遊びを管理・指導するのではなく、子どもの自主性を尊重し、必要に応じてサポートする「遊びの環境づくりのパートナー」として関わることが大切です。
🎭 学童期におけるごっこ遊びの大切さと面白さ
1. 社会的ドラマティック・プレーとしての発展
学童期前半(幼年期から小学校低学年にかけて)、ごっこ遊びは「社会を模倣する遊び(家族・お店・警察など)」として高度化します。役割モデルとなる大人(先生や保育者)が見せる「社会的振る舞い」を、子どもが主体的に取り込みながら遊びを展開する姿が観察されます。
この段階では、
-
役割取得と視点取得が進むことで、
-
仲間との関係調整やコミュニケーションが深化し、
-
最終的にはルール遊びへつながる認知や社会性の基盤となる、
という流れがあると考えられています。
2. 自己調整(セルフレギュレーション)の強化
幼児期に比べ学童期は「自分の感情や行動を調整する力」が一層求められます。その中でポジションを演じ切るごっこ遊びは、自己調整能力の向上と深く関連していると示唆されています。例えば、
-
役割を守るために「相互調整、我慢、ルールの遵守」が必要になり、
-
これが認知的・情動的な自制力を養う土台になる
という研究結果もあります。
3. 認知・想像力と問題解決力の向上
中学生以降の遊びは「構成遊び・ルール遊び」への移行が目立ちますが、ごっこ遊びによる「イマジネーション」「ストーリーテリング」「ものを別のものとして扱う象徴的操作」などは学童期にも継続して重要です。そこから以下のような効果が期待できます。
-
物語設計や役割による「抽象的思考」のトレーニング
-
想像力を使った問題解決・代替手段の創出能力
こうした能力は学習や集団活動における学童期の非認知能力(自己効力感・協調性・情緒安定)にも通じ、将来への基盤になります
4. 仲間との協働とコミュニケーション
ごっこ遊びは「共通の架空世界」を仲間同士で作り出し、ルールや役割を共有します。その過程で
-
他者と意図を共有すること(心の理論・相互視点理解)、
-
交渉、順番、対話、折衝などの社会的スキル、
といった社会性が育まれます。特に学童期は、集団遊びやルール遊びへの導入期として最適なタイミングです。
🧒 学童保育での実践ポイント
-
大人の関わり方:モデルとして「役割を示す」「適切な台詞で応答する」ことで、子どもが社会的やり取りを模倣しやすくなります。
-
素材と環境を調える:段ボールや小道具、衣装などを用意し、ごっこ遊びが登場人物・シナリオを豊かに展開できるよう支援します。
-
振り返りと対話:遊びの後に「どうしてその役を選んだ?」「困ったときどうした?」と問いかけることで、意図理解や自制力を言葉にする学びに繋げられます。
✅ 総まとめ
学童期におけるごっこ遊びの成果内容社会的視点取得とルール理解大人の振る舞いを模倣しながら仲間とのやり取りを学ぶ自己調整力の向上役割に沿った行動で自己制御が鍛えられる想像力・問題解決スキルの育成架空のシナリオを設定し、創造的に解決する力非認知能力の育成自信・情緒制御・他者協調といった未来につながる力
学童保育は生活時間が長くなる分、ごっこ遊びを続けやすい環境です。保育士がその世界に寄り添い、問いかけを通じて子どもの「なぜ」「どうした」を引き出すことで、より深い発達支援につながります。